相続税の計算方法と税率とは?計算例と、相続税対策を解説
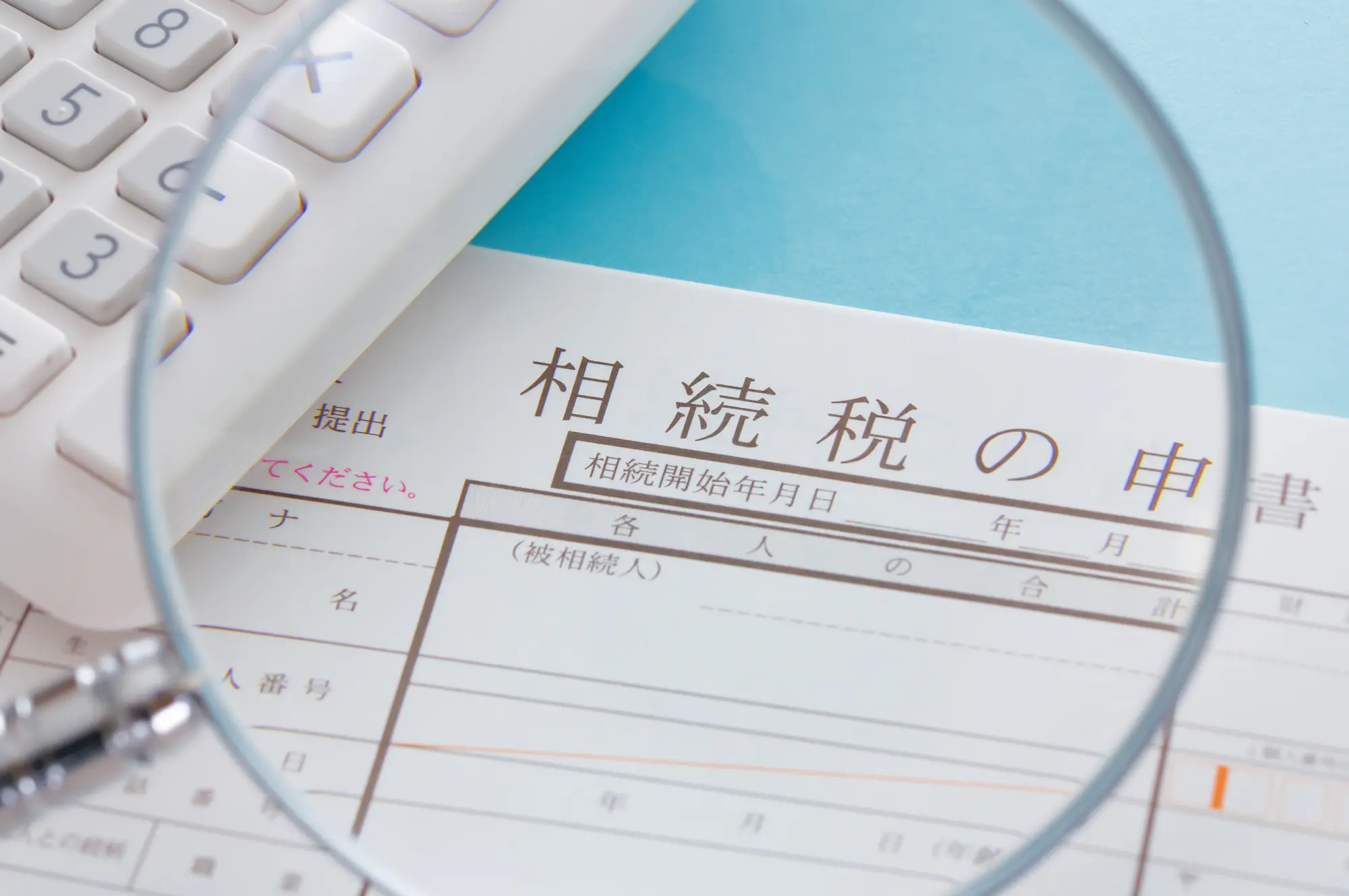
相続税とは、亡くなった方から相続した財産に課される税金のことです。聞いたことはあっても、まだ相続をしたことがない人にとっては具体的に金額をイメージすることは難しいかもしれません。「相続税って一体いくらかかるの?」「何か対策できることはあるの?」そんな疑問をお持ちではありませんか?
このコラムでは、相続税の税率の仕組みから、具体的な相続税対策まで解説します。今後相続することになった時に焦ることのないように、事前に相続税の知識を持っていると安心です。ぜひ最後までお読みください。
相続税とは、財産を引き継ぐ際に課される税金
相続税とは、亡くなった方(被相続人)から財産を受け継いだ方(相続人)に対して課される税金のことです。
相続税は「遺産総額から基礎控除額を差し引いた課税遺産総額」に、定められた税率を掛けて計算されます。この税率は、課税遺産総額に応じて段階的に上がっていく仕組みになっています。
相続税の基礎については、「相続税とは?基礎控除の仕組みから計算方式まで解説」もあわせてご覧ください。
相続税はどんなものが対象になるか?
相続税の課税対象になるものは、現金や不動産(土地・建物など)、金銭に見積もることができる全ての相続財産です。なお、国外にある財産も、相続税の課税対象となります。詳しくは以下のとおりです。
主な相続財産
原則として、被相続人が亡くなった時点で所有していたすべての財産が、相続税の対象となります。主な対象は下記のものです。
・現金・預貯金
・有価証券(株式など)
・不動産(土地・建物)
・貸与金
・知的財産権(特許権・著作権)
みなし相続財産
被相続人の死亡によって相続人が取得するもので、法律上相続財産とみなされるため、課税対象です。
・生命保険金 ※「500万円 × 法定相続人の数」までは非課税
・死亡退職金 ※「500万円 × 法定相続人の数」までは非課税
生前贈与財産
被相続人が、生前贈与していた財産に対しても、条件を満たしているものは課税対象となります。
・相続時精算課税制度を適用した贈与財産:被相続人の生前に贈与を受け、相続時精算課税を適用して贈与税の申告をした財産は、相続税の課税対象となります。
参考:国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」
・相続開始前7年以内の贈与財産:相続税の負担を不当に減少させることを防ぐため、相続開始前7年以内に行われた贈与は、相続財産として課税対象となります。
※相続前3年超7年以内に受けた贈与については、総額100万円までは相続財産に加算しない
相続税の課税対象外の財産・費用
・墓地・墓石、仏壇・仏具、神具など:これらは相続しても課税対象にはなりません。ただし、被相続人の死亡後に相続人が相続した財産から墓地や仏具を購入した場合は、課税対象です。
・債務(借入金・未払金・未納入の税金など)
・葬式費用(寺や葬儀社への支払い、通夜費用):ただし、被相続人の死亡後に購入した墓地・墓石、香典返し、法要の費用は葬式費用には含まれないため、相続財産から差し引くことはできません。
参考:政府広報オンライン「相続税はいくらから?基礎控除とは?相続税の基本を確認!」
相続税の計算方法と税率
相続税を計算するステップは、以下のとおりです。
|
1.課税価格から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を算出 2.法定相続人で按分する 3.2の結果から、それぞれの金額を速算表(後述)に当てはめて計算する。それらを合計し、相続税の総額を求める。 4.3で求めた総額を、実際の相続割合で按分する。 5.相続税額に加算や控除を行い、最終的な相続税額を算出する。 |
具体的な数字を例として、実際に相続税の計算を行います。
例えば、下記のケースの場合で計算方法を説明します。
|
【例:A家のケース】 被相続人の財産が8,000万円。 法定相続人が配偶者・長男・次男の3名で、それぞれ下記の金額ずつ相続した場合。 ・配偶者:4,000万円 ・長男:2,000万円 ・次男:2,000万円 |
関連記事:法定相続人とは誰を指す?範囲・順位・確認時の注意点を解説
ステップ1:課税価格から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を算出
亡くなった方の全ての財産の合計額を計算し、課税される総額を算出します。必要に応じて専門家の支援を受けることで、正確な数値を出すことができます。
課税総額が分かったら、下記の計算式で基礎控除額を求めます。
|
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数) |
なお、相続税は原則として、相続税の課税金額が基礎控除額を上回るときのみ課されます。
つまり、法定相続人が3人(配偶者+子2人)の場合、【基礎控除額=3,000万円+600万円×3=4,800万円】が基礎控除額です。このケースでは、相続税の課税金額が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。
次に、遺産の総額から基礎控除額を差し引きます。
|
【例:A家のケース】 遺産総額8,000万円は、基礎控除額(3,000万円+600万円×3=4,800万円)よりも高いため、相続税が課される。 8,000万円-基礎控除額4,800万円=3,200万円 |
ステップ2:1の金額を法定相続人で按分する
1の金額を法定相続分で按分します。
|
【例:A家のケース】 法定相続分は下記の通り。 ・配偶者:2分の1 ・長男:4分の1 ・次男:4分の1 <按分結果> ・配偶者:3,200万円×2分の1=1,600万円 ・長男:3,200万円×4分の1=800万円 ・次男:3,200万円×4分の1=800万円 |
ステップ3:速算表に当てはめて計算し、相続税の総額を求める
ステップ2で求めた金額を相続税の速算表に当てはめて計算します。それぞれの算出した税額を合計したものが相続税の総額です。
相続税を算出する際は、下記の速算表を用いて各人の相続税額を算出します。この速算表から、ご自身のケースにおける相続税額の目安を計算することができます。課税遺産総額が大きくなるほど、適用される税率も高くなる点に注意が必要です。
【相続税の税率(速算表)】
|
法定相続分に応ずる取得金額 |
税率 |
控除額 |
|
1,000万円以下 |
10% |
– |
|
1,000万円超から3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
|
3,000万円超から5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
|
5,000万円超から1億円以下 |
30% |
700万円 |
|
1億円超から2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
|
2億円超から3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
|
3億円超から6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
|
6億円超 |
55% |
7,200万円 |
参考:国税庁「No.4155 相続税の税率」
|
【例:A家のケース】 速算表を用いて計算する。 ・配偶者:1,600万円→速算表より、税率15%・控除額50万円 ・長男:800万円→速算表より、税率10%・控除額0円 ・次男:800万円→速算表より、税率10%・控除額0円 ↓ ・配偶者:1,600万円×15%-50万円=190万円 ・長男:800万円×10%=80万円 ・次男:800万円×10%=80万円 ↓ 相続税の総額=190万円+80万円+80万円=350万円 |
ステップ4:3で求めた相続税の総額を、実際の相続割合で按分
相続割合を求めて、それぞれの相続税額を算出します。
|
【例:A家のケース】 実際の相続割合を計算する。 ・配偶者:4,000万円/8,000万円=0.5 ・長男:2,000万円/8,000万円=0.25 ・次男:2,000万円/8,000万円=0.25 ↓ 各相続人の相続税額を算出。 (計算式:3の相続税額×実際の相続割合) ・配偶者:350万円×0.5=175万円 ・長男:350万円×0.25=87.5万円 ・次男:350万円×0.25=87.5万円 |
ステップ5:相続税額に加算や控除を行い、最終的な相続税額を算出
相続割合を求めて、それぞれの相続税額を算出します。
※相続した人が、被相続人の一親等の血族(代襲して相続人となった直系卑属を含む)および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額に2割加算されます。具体的には、被相続人の兄弟・甥姪は、親族であっても2割加算の対象となります。
【主な控除】
・配偶者の税額軽減:配偶者が取得した課税額が1億6,000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかからない。
・未成年者控除:相続人が18歳未満の場合は、18歳に達するまでの年数1年につき10万円が相続税額から控除される。
・障害者控除:相続人が85歳未満の障害者である場合は、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者である場合には20万円)が相続税額から控除される。
|
【例:A家のケース】 実際の相続税額は、下記のとおりです。 ・配偶者:0円(課税額が1億6,000万円以下のため、配偶者の税額軽減にあたる) ・長男:87.5万円 ・次男:87.5万円 |
このように、相続税額を計算することができます。
主な相続税の節税対策
相続税は、事前の対策を行うことでその負担を軽減することができます。ここでは、代表的な節税対策をご紹介します。
1.暦年贈与を活用する
暦年課税制度とは、年間の贈与合計額が110万円以下の場合、贈与税がかからない仕組みです。この非課税枠の中で生前から財産を贈与することで、最終的な相続税を減らすことができます。
ただし、前述の通り、相続開始前7年以内に行われた贈与は相続財産として課税対象となります。亡くなる直前に贈与した財産には、相続税がかかるため注意が必要です。
2.相続時精算課税制度を活用する
相続時精算課税制度とは、この制度を活用して贈与した財産は、贈与税が累計2500万円まで非課税になる特別控除です。この制度で贈与した財産は、相続税の課税対象となります。
しかし、相続税の計算の基準となる金額は、相続開始時ではなく、贈与時の額です。そのため、値上がりが見込まれる財産を生前に贈与することで、その差額の分の相続税を抑えられる場合があります。
また、2024年1月に制度が変わり、2024年1月1日以降に受けた贈与については、年間110万円以内ならば贈与税・相続税ともに非課税となる控除が追加で設けられました。
注意点として、この制度を活用した場合は1の暦年贈与が使えません。
3.不動産を活用する
【贈与税の配偶者控除】
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用不動産等の贈与を行った場合、贈与税の基礎控除額110万円のほかに、最高2,000万円まで控除できる特例です。
参考:国税庁「No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」
4.生命保険金の非課税限度額を活用する
前述の通り、生命保険金はみなし相続財産として課税対象となります。しかし、生命保険金のうち「500万円 × 法定相続人の数」までは非課税です。
死亡時の保険金の額と法定相続人の数を計算することで、相続税額を軽減できます。
早めの準備と専門家への相談が大切
相続税の税率は、課税遺産総額が大きくなるほど、適用される税率も高くなります。その計算方法は複雑で、かつ相続税の課税対象も多いため、何も対策をせずにいると、思いがけず多額の相続税が発生してしまう可能性もあります。
大切なことは、早めに相続について考え始め、情報収集を行うことです。そして、ご自身の状況に合わせてどのような対策が有効なのか、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
新潟相続のとびらでは、新潟で暮らす皆さまの相続のお悩みに寄り添い、未来のとびらを開く選択肢を、相続の専門家として幅広くご提案させていただきます。
ご相談は、下記のフォームからお気軽にお問い合わせください。
▼お問い合わせ・ご相談はこちら
https://www.souzoku-tobira.com/contact/

八百板 誠 税理士、行政書士、ファイナンシャル・プランナー
税理士法人万代つばさ 代表
新潟相続のとびらでは、私自身の税務署勤務時代のノウハウ、税理士・行政書士としてのスキルや経験、そして、弁護士や司法書士、土地家屋調査士といった各分野の専門家とのネットワークを生かし、幅広い相続のお悩みを解決に導いています。お客様の未来につながる選択をサポートできるよう、できるだけ複数の解決策を提示いたします。どうぞお気軽にご相談ください。